記事の内容
はじめに
2025年、アメリカでは再び「規制緩和」が大きなテーマになりました。航空、暗号資産、そして食品・飲料まで──。
その波は、日本にも問いかけを投げかけました。
「戦後から続く酒造規制、本当にこのままでいいのか?」
ビールや日本酒は、日本人の生活に欠かせない『暮らしの文化』そのものです。
しかし、この『一杯の自由』は、戦後長きにわたり奪われてきました。理由はただ一つ。財源確保のための過度な税金と統制でした。
自家醸造すら許されなかった戦後
戦後、GHQと日本政府は財源確保のために酒造業を徹底的にコントロールしました。
その象徴が「自家醸造の全面禁止」です。
ビールもワインも、たとえ趣味でも、家で造ることは法律で厳しく禁じられています。
発酵させたら、それは密造と見なされ即アウト。
この背景には、酒税法による国税庁の徹底した支配があり、税収という名の「鎖」で暮らしの文化を縛った現実があるのです。
クラフトビール市場の「とんでもない差」
1970年代、アメリカでは自家醸造(ホームブリュー)が合法化され、クラフトビール文化が一気に花開きました。
その結果が、現在の日米市場の絶望的な差として現れています。
- アメリカ:クラフトビール小売市場 約4.3兆円(約289億ドル)
- 日本:クラフトビール市場 わずか数千億円(シェア2%未満)
この数十倍にも及ぶ大きな差は、単なるビールの話ではありません。
では、日本が本当に失ったものは何だったのか?
損失は多岐にわたります。それは、「家でつくる自由」とともに生まれるはずだった、無数の起業、雇用、そして豊かな文化的な物語、その全てです。
もし自由だったなら──もうひとつの日本の姿
もし日本でも、もっと早い段階で規制が緩和されていたなら?
地元の人が仕込んだ「うちのビール」や「隣のどぶろく」が、居酒屋に並んでいたかもしれません。
家族の祝いに、父親が仕込んだビールをみんなで乾杯──そんな文化も育っていたかもしれません。
私たちが失ったのは、GDPだけの数字ではありません。
日常の暮らしを彩る文化的な深み、そして「豊かさ」の多様性そのものなのです。
今こそ「戦後の呪縛」を断ち切るとき
2025年、アメリカではトランプ再登板に伴い、再び「規制緩和」が大きなテーマになっています。
これは単なる米国内の話だけではなく、日本にとっても「見直しのタイミング」なのです。
戦後の名残で残ってきた古い規制。
そのせいで、生まれなかった味、生まれなかった文化、生まれなかった物語が、いったいどれだけあるか。
まとめ:次の一杯を、もっと自由に
戦後の酒税支配は、日本の酒造文化を何十年も遅らせました。
でも今、風向きは変わろうとしています。
次の一杯を、もっと自由に。
その自由を広げるのは、制度が変わるのを待つことではなく、私たち自身の「関心」と「行動」です。
さあ、まずは行動しましょう。最も簡単な一歩は――
- 地元のクラフトブルワリーを訪ねてみる。
- 国産のクラフト酒を意識的に選んでみる。
一人ひとりの小さな選択が、文化の芽を育て、戦後の呪縛を断ち切る力になるのです。
次回予告
第4回は「農地改革編」。
米を食べ、米から酒を造る――。
その根幹にあった日本の農業も、戦後の政策で大きく形を変えました。
「米を守る」はずの改革が、「酒を縛る」結果になった?
次回は、戦後農政と酒の意外な関係を追います。

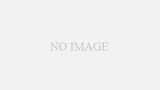
コメント